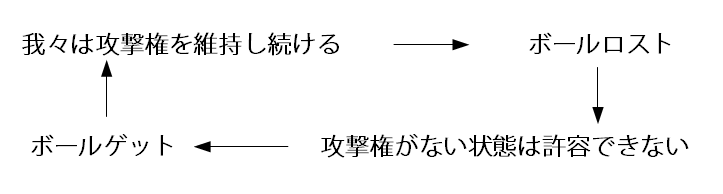今回は主に競技面から2020年8月末日の時点で、横浜F・マリノスはこの先どうするんだろうか、というポイントを主に綴りたい。
先ず、久しぶりにブログ記事を更新すると、あろうことか、随分サボっていましたね的な反応を受ける事がある訳だが、原則として書きたい事がある時に書く物であって、はてなブログから『お前、90日更新がないから広告貼り付けなぁ(笑)』みたいな、理不尽な所業を浴びようが、そこはブレる事はない。
書く以上は、書いた事、それは伝えたい事であり、その伝播という点でPVを求めるが、別に常時必要なものでもない。
この点で、個人的な感想ではあるが、昨今は試合の分析記事という物が増えている傾向を感じるが、テンプレートが用意され、製造しやすく、日々PVを得るのに良い手段だとして、その内容があまり刺さるものではない。
というのも、ざっと見た感じではあるが、その分野の第1人者には有る、何故分析をするんですか、何を伝えたいのですか、という目的が希薄だからではないかと思う。翻って、貴方にとって、そのPVは常時必要かね?みたいな。
そこに、数値には出にくい選手、その選手がいかに素晴らしいか伝えたいんだ!みたいな目的があれば、残るものがあると思うんですよ。
と何で書くんだ、みたいな話を無駄に長く触れるのも、先日、これぞ地元チーム、Myチームを語る素晴らしい記事だ!というのを久しぶりに見たので、面倒くさい事を言いたくなった。
伝えたい事がある記事は面白いんだよ、とにかく。
そして自分のモチベーションを振り返ると、このブログはスポナビ時代に始めた訳だけど、当時の状況として、マリノスに対して好意的なメディアが殆ど居ない、むしろ悪い事ほど面白がって書き立てられる事に対するカウンターとして、ファクトに基づく反論をしたかったという経緯があり、
その環境が、いまマリノスに触ればPV稼げる的な環境になって、まぁ去年に優勝して大きく変わったよね(笑)みたいな事もあり、最後に勝ち誇って勝ち逃げしておくか、次の機会までしっかりと爪を研いでおくか、みたいな状況であった。
一方で、混迷のシーズンも若干、先に対する見通しが、少なくとも競技面では立つようになったので、Twitterで垂れ流すには長過ぎるという理由で、一度、今感じている事をまとめる事にした。
ニューアマノの○○○○化
タイムラインとか見てると、みんな天野に対してちょっと厳しいんじゃないですかね。
気持ちの問題で、変化して帰ってきた今の天野と、喜田を組み合わせて、天野×喜田(※あいうえお順です意図はありません)=喜田純にすると、すごい選手になるんやないか、みたいな妄想も捗りますが、
私のもう一つの専門分野である、長い品種改良の歴史を持つ競走馬の世界的に、両親の良い所を伝えようとしたら、気性が悪くて、スピードが無く、脚の形も良くない、みたいに悪い所しか伝わらない事が多い訳で、安直な掛け算は危険なのです(真剣)
戦術的ポジションニングが苦手で、狭いスペース、敵の選手間で受けるのが苦手で、いざ自分の前がオープンになっても、なぜか機能停止してしまう、みたいな。
この点で、戻ってきたニューアマノは光る要素を見せつつも、「うーん、何かハマらない」感が漂うわけですが、今季は特にエリキ問題が顕著ですが、ポステコグルー監督は獲得してきた選手を直ぐにマッチさせるのが上手い一方で、どうみても向いていない謎の運用にやたらこだわる性質があります。
エリキも辛いですよね、昨年を観てない人にしてみたら、優勝の立役者?何が良い選手なの、みたいな
この適した運用なのか、という点で、ある意味、天野は最適な位置を探し続けてる選手ではないかと考えます。
偉大な10番の先輩と比較され、マルコスや三好がいる中で扇原と2.5列目のポジションを争う事になり(不満で飛び出したけど)、今はマルコスが突き抜けたクオリティを示す中、更に渡辺の様なポジショナルプレーの申し子のような世代と争う。
いや、でもさ、今のニューアマノのプレー指標を見ると適材ポジションは、マリノスがオフシーズンに失った重要なピースと合致するんじゃないの?みたいに思うわけです。
DATA by フットボールラボ https://www.football-lab.jp/
1366分 インサイドと2.5列目でプレーした2019年の天野

そして、2020年帰ってきたニューアマノ 482分

この傾向、どっかでみたよな…!?
2019年左ウイングで730分プレーしたマテウス

現状、天野のプレー指標に類似するのは各チーム、サイドハーフの選手ばかり

ニューアマノ、左ウイングが合致するんでは?
まぁでもインタビューの受け答えを見ると、監督は怖いですよね。
自ら志願しても、全く別のテーマについて話し出したりされたら(笑)
ただ、これは同時に、エリキや他の選手がハマらずに仕方なく高野を活用している、故に、チームの中で左サイドバックだけが疲労度やばくね問題を解決する重要な運用になりそうである。
また、真ん中を一つ開ければ、大津や仙頭も活用できるし、更に左サイドバック問題は最早、質を落としてでも何とか数を間に合わせないといけないかもしれない。
なにせよ、とんでもない日程が待ち受けるからだ。
マリノスはシーズンを完走出来るのか!?
気持ちとして高く置く、より良い位置を目指すってのはいいとして、精神は物理を越えられないので、現実問題、マジで無理じゃないですかね。
マリノスが参加する、セントラル開催が告知されたACLの日程が以下になります。
会場未定(開催国未定と同義)
10月23日、10月26日、10月29日、11月1日(これは絶対にやる総当たり戦)
で、勝ち上がったらそのままの会場で、11月4日にベスト16を開催
一発勝負のルヴァンカップは2試合勝つと決勝進出として、現在ある帰国者14日間の待機要請を、帰国即検査して陰性ならOKみたいな、特例でゼロにする事が出来ないと、ACL組の出場は不可能なんですよね。
またACLは、11日間で最大5試合を戦う想定でスカッドを組まなければいけないので、少なくともGK3人の22人体制で現地入りしないと戦えない、20人でいけるか?
となると、GKはパクと中林、ユース選手でACLに行って、梶川とユース選手で決勝戦みたいな。
ここで、準決勝が10月7日開催に対して、ルヴァンの選手登録は10月2日締め切りなので、勝ち上がったらオビ・パウエルを呼び戻す、ということは出来ない為、ルヴァン準々決勝を勝ち上がった時点で追加レンタルするしかない。
また、リーグ戦も11月11日、14日に入っており、帰国後は14日間待機となると、こちらもそのままACL組の出場は無理になります。
更にACLを勝ち上がった場合は、25日に準々決勝があり、勝ち上がれば28日に準決勝。
この場合、ベスト16突破の時点で、28日の川崎戦が18日に移動するので同日開催は避けられますが、14日待機要請を回避する方法が無い場合に受ける影響は、カップ決勝以外にも、リーグ戦3試合が確定します。
11月5日(帰国日)→19日?
更に、更に、ACLを決勝まで勝ち上がると12月5日に開催が予定されている為、同日予定のホーム鹿島戦は当然開催できず、この試合は12月1日に移動しますが、ACLに出場する選手は恐らく誰もこのホーム戦には出られないでしょう。
だって準決勝と決勝戦は別の国でやるんだもの(多分)
11月28日(どっかの国)準決勝 これは東アジア地区同士の対戦なので普通は東アジア
12月1日 横浜で鹿島戦
もう14日の待機要請すら関係ねぇ!感じになってきました(皆がんばれ)
この時点で、リーグを後ろにスライドできる、開いてる日程は12月9日のみ、条件付きで両チームが天皇杯に出場していなければ(なおかつ1位、2位の順位決定に関係がない順位なら?)リーグ全日程終了後の、12月23日、27日に出来なくは無い感じですかね。
オフサイドの誤審で、あーだこうだと騒ぐとか、もう、どうでもよくないですかね。
もう今季は、公平に競技力を競うシーズンじゃないんですよ。
皆で無事にゴールまで辿り着こうぜってシーズンです。
もちろん入場制限により、大幅な減収減益は必至な訳で、とにかくみんな生き残ろう
Twitterはこちらです